今回は定期データの更新記事で、
「実際に各高校に行く人はどれぐらいの内申点を取っているのか?」
「各高校の偏差値はどれぐらいなのか?」
「内申点と偏差値の関係性はどうなのか?」
というところの最新データをご紹介します。
2024年の最新データをまとめました。
記事は以下からどうぞ。
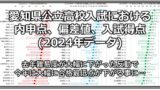
なお、分析対象の学校に関しては、愛知全県模試の合格者平均偏差値が55以上を対象としました。
合否ルールについて
今回の入試から愛知県の公立高校入試の合否判定ルールが変更になっています。
詳細はこちらの記事をご確認いただければと思いますが、やはり最も影響が大きい変更としては、
「入学試験がマークシート式になった」
というところでしょう。
このあたりの変更点がどのように影響しているか、今回の試験では注目されていました。
参考となるデータ
愛知県の公立高校の内申点や偏差値の目安については、様々な学習塾でデータを出していますが、データの母数が大きく信頼性が高いのが「愛知全県模試」の結果データではないでしょうか。
愛知全県模試は下記の通り、受験する人数が多いことを強みに挙げていますが、追跡調査により各校の合格者内申点の平均値等を出しているのが大きな特徴です。
引用元:愛知全県模試公式ホームページより
このデータは愛知全県模試を行ったことのある塾向けのみに「愛知全県模試 追跡調査NEXT STAGE」として展開される資料で、一般の方が目にする機会はあまりないです。
しかし、近年はこの資料をベースとした分析を行い、様々な情報とともに紹介している塾が沢山あるため、ある程度の情報を知ることができるようになっています。
いつもご紹介していますが、かなり詳細な分析&データ公開をしている塾の一つとして、【名学館小牧新町校のブログ】があります。
ここは毎年各校の内申点平均値等多数のデータを掲載しており、より詳細なデータを見たい場合はこちらを確認すると良いと思います。
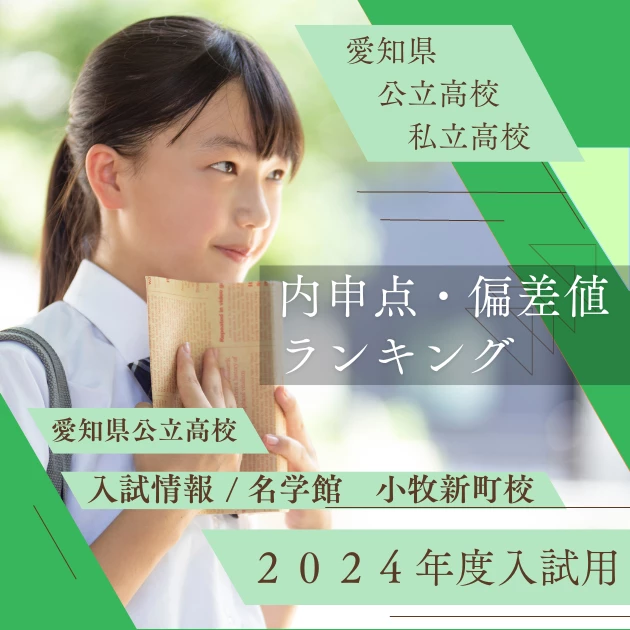
なお、今回からは普通科に加え、進学校的なカリキュラムを有する(進学実績の良い)専門学科も対象にしました。
各種データ抽出の結果
内申点の状況
各校の内申点の状況は以下のようになっています。
この数値は合否判定で使う90点満点ではなく、2倍する前の45点満点の数値ですね。
※◯のプロットが合格者の内申点平均値、棒グラフ部分が最大値と最小値の範囲を表す
※学校名右側の[]内は2022年のデータからの差分を示している
※順番は愛知全県模試合格者平均偏差値上位順出典元:2023年愛知全県模試 追跡調査NEXT STAGEより
上記の通り、上位校合格者の内申点はかなり高得点です。
昨年と比較すると、内申点の合格者平均は下がっているところが多いです。
ここ数年は合格者内申点の平均値は上昇していたのですが、今年は落ち着いたという感じ。
最大、最小、平均値のみだと判断が難しいですが、イメージとしては、
- トップ10の学校を目指すのであればオール4以上は欲しい
- トップ5校以上を目指すのであればオール5に近くないと厳しい
というのは変わっていないですね。
勉学5教科でオール4以上を取るのは努力次第で想像ができるとしても、それ以外の4教科(保健体育、技術家庭、美術、音楽)でもオール4以上を確保するというのは相当なハードルを感じます。旭丘や明和等への進学実績を積み上げたい中学校側の思惑を感じるような感じないような…
このあたりは再三触れていますが、
「子どもの性格等で向き不向きが確実に存在する試験方式である」
というのは頭に入れておいた方が良いです。
入学試験の得点の状況
各校の入学試験の得点状況は以下のようになっています。
(各教科22点満点x5教科で110点満点のテスト)
また、合否ルールのパートでもご紹介しましたが、今回ピックアップしている学校の大半は合否判定に入学試験重視のパターン(入学試験得点x2倍)を採用しています。
なお、2024年春の入試からは、今回ピックアップした高校で”入学試験の得点x1.5倍の方式”を採用するのは春日井高校のみとなる予定です。
※◯のプロットが合格者の内申点平均値、棒グラフ部分が最大値と最小値の範囲を表す
※学校名右側の[]内は2022年のデータからの差分を示している
※順番は愛知全県模試合格者平均偏差値上位順出典元:2023年愛知全県模試 追跡調査NEXT STAGEより
こちらも内申点と同様、上位校は8-9割の得点が当たり前、という感じになっています。
試験問題自体が難問奇問がほぼない状況から、やはり突出した能力を有する生徒よりも、ミスや穴のない生徒を選抜する趣向が強いように感じます。
問題と解く生徒側からするとミスの許されない本当にプレッシャーのかかる試験だと思います。
今回の注目ポイントであった
「マークシート方式への変更による影響」
もこのデータから読み取る事ができますが、上位校でも大半の学校で上昇した、というのが結果として現れています。
これは、以下の通り受験者全体の平均点も上昇傾向であることから明らかであり、特に今年の数学は平均点の上昇が顕著でした。
出典元:愛知県HPより
また、昨年との差分は平均値しかデータとしてグラフに出していませんが、合格者最低点がかなり上昇しているのも今回の変化点として大きいです。
合格者最低点変化の例を挙げると、
- 旭丘:91点→96点
- 明和:86点→93点
- 向陽:83点→93点
- 菊里:77点→90点
という感じ。
もう少しわかりやすく可視化すると以下のようになります。
※◯のプロットが合格者の内申点平均値、棒グラフ部分が最大値と最小値の範囲を表す出典元:2022年および2023年愛知全県模試 追跡調査NEXT STAGEより
上図の通り、瑞陵以外はますますミスの許されないテストになってしまっています。
偏差値の状況
各校の合格者が愛知全県模試においてどのような偏差値だったか、というデータは以下の通りです。
※◯のプロットが合格者の内申点平均値、棒グラフ部分が最大値と最小値の範囲を表す
※学校名右側の[]内は2022年のデータからの差分を示している
※順番は愛知全県模試合格者平均偏差値上位順出典元:2023年愛知全県模試 追跡調査NEXT STAGEより
偏差値のトップは旭丘高校ではなく、向陽の国際科学になっているのに驚きました。
(最初のグラフから偏差値順で掲載していたのでネタバレしていましたが…)
やはりこちらもトップ10の学校は偏差値60以上は当たり前、というような状況になっており、かなりハイレベルです。
なお、偏差値はイメージがしづらいですが、仮にテスト結果が正規分布だったとすると、「偏差値60というのは上位15%以内」というイメージと考えると、そのレベルの高さが理解しやすいのではないでしょうか。
====
以上、今回は
[2023年データ]愛知県の公立高校受験の内申点や入試得点、偏差値まとめ
についてご紹介しました。
マークシートへの変更だけが理由ではないと思いますが、特に合格最低点が顕著に上昇しているのは今年の大きな変化点でした。
この傾向が続くとすると、より「ミスのない生徒」が上位校では求められていくことになります。これって公立中高一貫校で実施する「チェンジメーカーの育成」と親和性悪くないですかねぇ…
チェンジメーカーって”とにかくミスのないように”という姿勢とは相反する気がするんですが。
面白かったらTwitterでいいねやリツイートお願いします!
皆様の参考になれば幸いです。











コメント
こちらのサイトを今日知って、主に中学受験の記事を読み漁りました。
あまりよく分かっていなかった試験日程を可視化してくださりありがとうございます。
どの記事も読みやすく、理解しやすいようになっているので本当にありがたい気持ちになりコメントを書いています。
現在小1の娘が中学受験するかもしれないので、また参考にさせていただきます。どうかそれまでこちらのサイトを継続していてほしいです。
コメントありがとうございます!
こういうコメントをいただくと、モチベーションも上がるので本当にありがたいです!
中学受験系の記事は、少なくともあと4年程度は(自分自身のためにも)調べる予定なので、記事更新もしていくつもりです。
今後ともよろしくお願いいたします。