昨日のランキング記事でも少し触れましたが、2022年の名古屋市プレミアム商品券である
- 名古屋で買おまい★プレミアム商品券(紙版)
- 金シャチマネー(電子版)
の情報が更新されましたのでご紹介します。
※2022年4月23日更新
利用可能店舗等の情報が公開されたので、
- 電子版と紙版の違い
- 上記違いから考える電子版と紙版を選ぶポイント
- 大手チェーンの電子版対応状況
をまとめました

今回の内容をザックリとまとめると以下のようになります。
- ポータルサイトが開設された
- 応募期間は2022年4月下旬から2022年5月下旬の予定
- 利用期間は2022年6月下旬~2023年1月下旬の予定
- 電子版でネガティブな情報が出てきた(利用可能店舗数が少なくなる可能性あり)
詳細は以下をご確認ください。
2022年名古屋市プレミアム商品券の特長
今年は河村市長が市長選対策に色々と公約を掲げた関係から、プレミアム商品券の内容が非常に豪華になっています。
既にご紹介している内容のおさらいとなりますが、その特長は
- 還元率が30%という過去類を見ない高還元率(1口1万円で購入し1.3万円利用可能)
- 合計168万口を発行し、昨年の2.5倍超の発行数
- 今年から電子版が導入され、電子版は1円単位で使用できる
- 1人5口(冊)まで購入でき、最大還元額は1.5万円/人となっている
といった感じです。
2021年のプレミアム商品券が2020年の6倍超の発行数だったので、今年はさらにその2.5倍超発行し、そのうえ還元率も1.5倍なので、かなりの税金が投入されている施策になっています。
決して安くない住民税を納めているので、こういう還元される施策は逃さず参加したいところです。
スポンサーリンク
今回の新情報
今回の新たな情報は
- ポータルサイトの開設
- 商品券/施策の名称
- 募集開始日/期間の目安
- 利用期間の目安
といった内容で、そこまで詳細な内容は語られていませんが、以下に詳細をご紹介します。
ポータルサイトの開設
以下の通り、今回のプレミアム商品券の公式サイトが開設されました。
詳細はまだ何もない状態ですが、3月7日に紙版、電子版の特設サイトもオープン予定となっているので、今後も継続してこのサイトから情報が発信されていくようです。
ただ、実は応募期間等の情報は上記特設サイトにはなく、名古屋市のホームページ上でのみ確認が可能になっていたりするので、現時点では色々なところから情報を集める必要はあるかもしれません。
以下は名古屋市ホームページ内にある2022年の名古屋市プレミアム商品券のページです。
こちらから応募期間等の情報は確認できました。
商品券/施策の名称
これまで、名古屋市のプレミアム商品券は、
「名古屋で買おまい★プレミアム商品券」
という名称で展開されていましたが、今回は、
- 紙版:名古屋で買おまい★プレミアム商品券
- 電子版:金シャチマネー
という別の名称、施策として進めるようです。
引用元:名古屋市プレミアム商品券公式サイトより抜粋
上記の通り、特設サイトも異なるものが用意される可能性が高いです。
自分が紙版、電子版のどちらを選ぶかで、応募の方法等が大きく変わってくるためこのような措置になっているのだと思いますが、間違えないように気をつけたいところです。
紙版の名称よりは良い気がしますが、電子版の「金シャチマネー」という名称はどうなんでしょうか…
募集開始日/期間の目安
これは、既述の通り名古屋市のホームページに記載があり、
応募期間:2022年4月下旬から2022年5月下旬
となるようです。
抽選なので焦る必要はないですし、応募期間は1ヶ月程度はあるので、比較的余裕がある設定になっていると思います。
利用期間の目安
こちらはポータルサイトにも記載がありますが、
利用期間:2022年6月下旬~2023年1月下旬
を予定しているようです。
2021年は8月スタートだった事を考えれば1ヶ月以上利用期間が長くなっており、購入金額(口数)にもよりますが、比較的余裕を持って使える期間があると考えられるのではないでしょうか。
その他の情報
現時点では、商品券を受け取る側の参加事業者向け情報がメインとなっていますが、そこから以下の情報が読み取れました。
- 利用できる店舗は紙版と電子版で異なる
- 紙版と電子版はどちらか一方を選んで応募する
- 電子版は店頭に設置されたQRコードをスキャンして利用するタイプ
引用元:名古屋市プレミアム商品券公式サイトより抜粋
利用できる店舗は紙版と電子版で異なる
上でご紹介した表の最下部を見ると、
“「両方参加」 または 「いずれか一方のみ参加」を選択できます”
という記載があります。
これは、参加事業者(商品券を受け取る店舗)が
- 電子版・紙版両方使用できる
- 電子版のみ使用できる
- 紙版のみ使用できる
の3パターンのどれかを自由に選択できるということです。
これには、非常に大きな意味があり、電子版の方が利用店舗が少なくなる可能性が高い事を意味します。
というのも、Go Toトラベルのクーポンも紙版と電子版の選択制でしたが、明らかに紙版の方が利用可能店舗が多いという実績があり、これを考えると電子版が不利になる可能性を否定しきれません。
もちろん、河村市長は元々電子版を推していただけあって、電子版は入金スケジュールが優遇されているなどの利点は店舗側にはありますが、
「なんかよく分からないから今までと同じ紙のやつだけでいいや」
となってしまう気がしますね…
(参考)Go toトラベルの紙版と電子版の利用可能店舗数の違い
下記サイトからGo toトラベルのクーポン利用可能店舗が検索可能ですが、試しに名古屋駅周辺で紙版と電子版の利用可能店舗数を調べてみました。
結果、
- 紙クーポンが使える店舗:3,780店舗
- 電子クーポンが使える店舗:2,308店舗
となりました。
※概ね名古屋駅が中心に来るようにし、縮尺はマップにアイコンが表示される最も広範囲が表示可能な縮尺を使用
つまり、
Go toトラベルのケースでは、電子版の方が3-4割程度使える店舗が少ない
という事です。
個人的には比較的規模が大きい店舗であるビックカメラもGo toトラベルでは紙版のみになっているのが非常に気になりました。
(今回は対応してくるかもしれませんが、高額商品が購入できる店舗なので、もし電子版非対応となったら痛いです…)
もちろん、上記の通り今回は店舗側にとっても電子版が優遇されている面がある等、Go toトラベルのケースがそのまま当てはまるわけではないですが、紙版か電子版かを選択するにあたっては頭に入れておいた方が良い情報だと思います。
電子版は店頭に設置されたQRコードをスキャンして利用するタイプ
これは既存のQRコード決済でも比較的小規模な店舗で利用される
「レジに置いてあるQRコードを自分でスキャンする方式」
を利用する、という事です。
(自分のバーコード/QRコードを読み取ってもらう方式ではない)
来年以降も継続して行われるか不明の決済ではこの方式しかないと思いますが、この方式は以下のメリットとデメリットがあります。
【メリット】
- 印刷されたQRコードを置くだけで準備が完了する(導入にかかる時間が短くて済む)
- 店舗側の導入コストがあまりかからない
【デメリット】
- 金額を手入力しなければならない/誤入力に気をつける必要がある
- 売上を確認するのに少し手間がかかる(PC等を操作する必要がある)
我々利用者側にとっては、金額の手入力が若干面倒で、店舗側にとっても売上確認にPC等が必要だったり誤入力リスクがあるため、ネガティブなイメージを持たれてしまう可能性はありそうです。
(上で説明した、「電子版の方が利用店舗が少なくなる可能性が高い」というのもこのあたりが理由の1つとして考えられそうです。)
紙版と電子版のどちらが有利なのか?
こちらについては以前考察した以下の記事に書いていますが、
「現時点では紙版の方が有利」
です。

上記の記事の通り当選確率は現時点では紙版の方が有利なうえ、今回判明した通り、電子版の方が利用可能店舗が少ない可能性があるので紙版の方が有利だと思います。
個人的には紛失リスクがある紙を持ち歩きたくないですし、1円単位で使用できる電子版は魅力的なんですけどね…
=======
今回は以上です。
3月7日以降、特設サイト等で新情報が出たらまた更新します。
皆様の参考になれば幸いです。

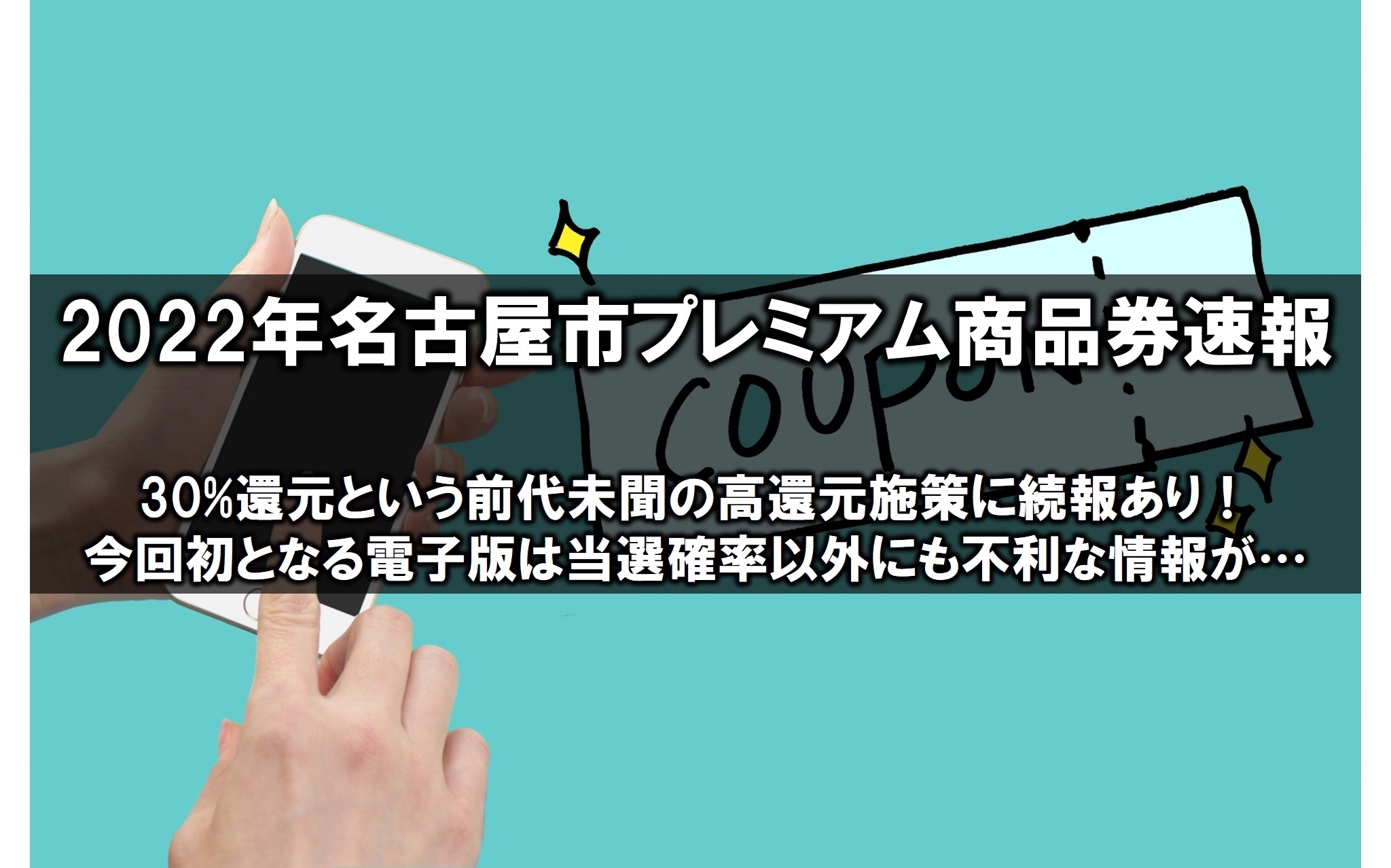



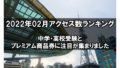

コメント